



人間のペットに対する事故の典型が、ペット産業(医療、ホテル、美容等)上のトラブルです。この場合には、咬傷事故のように偶発的な事故ではなく、飼い主が一定の事務処理をペット事業者に委任するという契約関係に基づく事故なので、受任者であるペット事業者は、善管注意義務(民法644条)を負っています。
ここでは、トラブルが多いペットの診療契約について詳しく説明します。
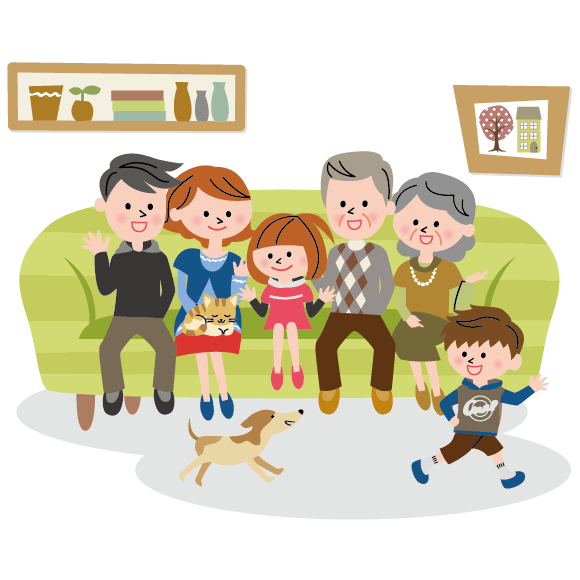
一言でいうと、ペットが加害者から被害者に変わってきました。
咬傷事故の比率よりもペットショップ、動物病院、ペットホテル、ペット美容院といったペットが取引の対象とされる場面でのペットの障害事故(疾患、怪我等)の比率が増えてきました。
背景には、ペット産業の急激な市場拡大とそれに追いつかない専門的スタッフや設備の不足や飼主の認識の高度化が挙げられます。
真実を知ることと交渉材料の収集は分けて考える必要があります。交渉材料の収集は交渉目的に沿ったものでなければなりません(目的適合性)。
当事務所に相談に来る方の多くがたくさんの資料を準備されています。真実を知るために大変な労力を使ってご苦労されています。飼主にその傾向が見られます。しかし、どんなに真実を知ろうとしても限界があります。それは相手方の説明がなければ真実が分かりませんが、相手方の説明では到底納得が出来ないからです。
ここで、資料収集の目的を考える必要があります。資料収集の目的が真実を知ることであれば良いのですが、相手方に謝罪や賠償を求める場合、相手方との間のトラブルを沈静化したい場合、将来的に改善策を検討したい場合などのそれ以外の目的の場合にはそれに沿った範囲で資料収集をし、早くご相談に来られた方が、後日の交渉のためにエネルギーの節約になります。
まずは必要不可欠な資料を準備した上でできるだけ早期に弁護士に相談して下さい。
弁護士の相談によって交渉戦略を立て、戦略の目的に沿ってそれ以外の資料を準備した方が効率的です。
契約関係を証明する資料(診療契約書、売買契約書、サービス提供契約など)とペットの障害(疾患や怪我など)の内容や程度が分かる診断書や診療記録などです。
何かしらの契約を結んだからこそ、代金を支払ってペットを購入したりサービスを受けたのですから、その契約の成立や内容が分かる契約書などの資料が基本資料として必要です。
ところが、業者によっては契約書も満足に揃えていないところがあります。
動物愛護管理法上の飼養方法に関する細かい注意書きは作ってあるのですが、ちゃんとした契約書は作っていません。
これでは契約内容が分からないので解釈を巡ってトラブルが起こります。
事業者はトラブル防止のために、飼養者はトラブルが起きたときの権利義務関係を事前に知っておくために契約書は必要不可欠となりますが、まさにトラブルが起きたときには基本的な紛争解決基準となります。
ペットに障害があるか否か、障害の程度は責任問題の前提となります。診断書、診断記録、診療明細、領収証などの資料が考えられます。
また、「障害」は人によって評価が変わる可能性がある価値的概念なので、その内容・程度が獣医学上の障害といえるのか、責任追求の対象となる損害に該当するのかといった観点から検討することも必要であり、獣医学上の文献、行政や学会の参考資料がなどが意味を持ちます。
もっとも、これらの資料は最初から全部揃っていることは稀なのでそれほど心配する必要はありません。要するに、資料探しに時間を費やすよりも、少しでも早くご相談に来て欲しいのです。ご相談の中で足りない資料や準備する資料の打ち合わせをするのが望ましいと言えます。
飼主側も事業者側も感情的な表現や相手方を非難する表現は避けた方が良いと思います。
信頼関係が崩壊し、交渉決裂してから、裁判所の力を借りないで円満解決を図ろうとしても困難なことが多く、また、双方の協力による資料収集も難しくなるからです。その結果、交渉戦略の選択肢を自らが狭めることとなります。
そして、必要不可欠の資料を準備した上で、早期の相談を行い、相手方に対応することになりますが、2②で指摘した、相手方の交渉方針の調査・分析が必要不可欠となります。
相手方がどのような考えに基づいてどのような交渉を行うのか予測して、それに対応した適切な交渉戦略を立てる必要があります。そのためには相手方の交渉方針の調査・分析をすることが不可欠になります。
この問題は「法交渉心理学入門(連載)」のテーマとなりますが、ペット障害事故特有の問題もあるので、相手方の交渉方針の調査・分析については次回に取り扱います。
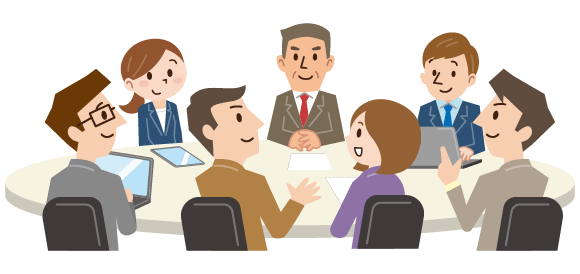
前回は最初の相談までの準備について述べました。
交渉の心構えとして、飼主側も事業者側も感情的な表現や相手方を非難する表現は避けることが大切です。
信頼関係が崩壊し、対立関係が全面に出ると交渉による解決の選択肢がなくなり、裁判の選択肢しか残らなくなります。多くの選択肢があった方が合理的効率的な解決を図ることができます。
次に、相手方がどのような考えに基づいてどのような交渉を行うのか予測して、それに対応した適切な交渉戦略を立てる必要があります。
相談を受ける弁護士には飼主の立場と事業者の立場の両方の知識と経験があることが必要です。
何故ならば、ペット問題の解決は裁判ではなく交渉と合意によることが望ましく、そのためには弁護士は両者の立場や考え方に精通していることが必要だからです。また、裁判「訴訟」による場合も双方の立場を経験していれば相手方の行動が予測できるからです。
この問題は「法交渉心理学入門(連載)」のテーマとなりますが、ペット障害事故特有の問題もあるので、相手方の交渉方針の調査・分析については次回に取り扱います。
色々ありますが、ここではそのうちの2つを紹介します。
第1に、最初から訴訟による交渉を試みる場合を除いて、通常は相手方に与える刺激の少ない信頼戦略から始めること。それに対する相手方の反応に対応して徐々に刺激の強い対立戦略に移行すること。
少しでも交渉の選択肢を減らさないため、交渉の初期は相手方の人格特性が不十分のため強い刺激を与えると相手方の強い反応(対立)につながる危険があることからです。
第2に、初期の交渉は面談や電話等の口頭による交渉よりも交渉専門家の指導を受けた文書による交渉が望ましいこと。感情的対立を避け、あいまいな言葉による行き違いを避けるためです。
ペット障害の事例は訴訟よりも合意による解決が望ましいので、いずれも交渉の初期においては相手方に与える刺激を極力減らして信頼関係を維持することが大切です。
しかし、本人交渉の場合は当然ですが、ほとんどの代理人が法交渉心理学の知識も経験もなく、ペット訴訟の知識や経験もなく、事業者側と飼養者側双方の経験がないため、代理交渉の場合であっても合意による解決のチャンスを失い、泥沼の訴訟の道を安易に導いてしまう。事案がネットやマスコミにまで拡散して事業者側の信用や評判が毀損される。
ペット訴訟による当事者双方のダメージは訴訟を回避することによって軽減することができるのにそのチャンスを初めから逃してしまっています。
確かに、当事者双方の代理人を長年勤めてきた経験からすると、交渉と合意による解決よりも訴訟(裁判)による解決が相応しい場合があります。
そのような事案の場合には徹底的に訴訟をすれば良い。
しかしながら、賠償金や制裁を望んでいない飼主、相手方に誠意ある対応を望んでいるだけの飼主など数多くいます。事業者がやみくもに三下り半的な法的文書を送れば良いわけではありません。
訴訟によらない信頼できる第三権威者の仲介による交渉と話し合い(裁判所の調停や弁護士会の斡旋仲裁)による合意で紛争の実態に応じたオーダーメイドの解決を実現することが最も適切な紛争解決手段となります。
2つのポイントでお伝えしたように交渉の開始(初動)は信頼戦略に基づく通知文書の作成から始めることが大事です。
この場合大事なことは内容と表現を区別することと送付方法です。
同じ内容でも表現方法を変えると相手方に与える印象(刺激)が変わることは日常よく経験しますが、これを戦略的に意識的に行うのです。
文書の場合は文字以外の表現方法が使えないので一語一語細心の注意を払って戦略的に書かなければなりません。
自分が言いたいことを書くのが文書の目的ではありません。相手方に交渉と合意による解決を図る意欲を起こさせるのが目的なのです。
また、送付方法も相手方の受ける刺激の強弱を予測して複数の中から最適な方法を選ぶ必要があります。
通知文書の作成は臨床の問題であり、実際の事案に応じて具体的に検討する必要があります。
再度強調しますが、具体的な個々の事案に応じて、相手方と今後どのような関係をどのような過程で築いていきたいのかをイメージしながら作成することが肝要なのです。
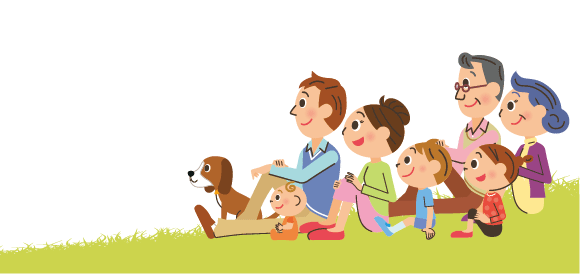
数回に分けて実際に扱った事件の解決事例を紹介したいと思います。
もっとも、多くの取り扱い事例の中の解決事例となるとある程度の類型化ができます。
実際の事例は事実関係や法律関係が複雑ですが、分かりやすい読み物というこの連載の目的に合わせて紹介したいと思います。
ペットショップから買ったペットに先天性の疾患が見つかったことによる損害賠償請求の依頼を飼主から受けました。この類型の事案はいくつも関わりましたが、いずれにも共通する主要な争点(論点)は、①契約による責任の減免の可否②保険の適用の可否③事業者の販売前の過失の有無④将来の治療費の請求の可否⑤慰謝料その他の損害賠償請求の可否です。
ここでは、全部について触れることはできないので、③、④について説明します。これらが訴訟や交渉において激しく争われるからです。
ペット販売契約の解除・合意解約の手法を使うとペットと購入代金の返還という方向で手続きや協議が進められます。
しかし、実際はそんなに簡単ではありません。
販売契約の解消→ペットと代金の返還という方向は、ペットを販売契約の対象とする民法上の「物」の考え方が前提にあるのでシナリオ通りには進みません。実際は、飼養者は、ペットに対する愛情と返還後のペットの適正飼養の不安からペットの継続飼養とペット購入後に発生する将来の治療費を請求し、ショップは、販売契約書の条項や法律論を根拠にペット代金を超える金銭の支払いには消極的です。
この場合の双方の利害調整に関する法律やルールは残念ながら用意されていないので、判決での解決では適切な解決を図れず、和解や合意による解決が試みられることになります。
飼養者側の代理人として訴訟を提起し、被告ペットショップの販売前のペットの健康管理方法の過失の存在を立証しました。
私は、事案によって訴えを起こす裁判所を通常部にする場合もあるし、医療専門部にする場合もあります。
原告代理人として、被告に対して、裁判上の送付嘱託又は調査嘱託の申立てにより、健康管理に関する内部資料の開示を強制し、被告の従前の主張や証拠との矛盾や虚偽を主張し、被告のペットの健康管理方法に過失があったことを明らかにしました。
被告側としては、その場しのぎの対応に終始し、訴訟早期での内部資料に基づく一貫した訴訟戦略の策定を行うべきでした。
このケースでは、訴訟継続中にペットの治療が終わったので将来治療費の金額を確定することができ、和解によって支払ってもらうことができました。
ペットに先天性の疾患が見つかった場合には訴訟上の和解によって解決する場合が多いのですが、双方の代理人と依頼者に交渉マインドがあったので訴訟前の合意によって解決することができました。
この場合には過去の事実関係の存否に拘泥するのではなく、訴訟の場合と交渉合意の場合の経済面、労力面、時間面の損得を冷静に検討する将来志向的な姿勢が必要となります。
一般に交渉は書面の受発信から始まりますが、私が書面を作る場合には将来の交渉を合理的かつ円滑に進めるために、弁護士の意見として、交渉方法のルールの提案を予めしておきます。いわば、「交渉のための交渉」です。そうでないと継続的な交渉が期待できないからです。
ペットの怪我や疾患のケースは、裁判所での話し合いである民事調停の利活用が適切な場合があります。私の経験上もデメリットよりもメリットの方が多いと思います。しかし、実際は、双方の交渉マインドの欠如や当事者が過去の事実関係や相手方の責任を問題とする場合が多いので訴訟での和解が選択される傾向にあります。

(1)最近のペット問題の特徴の一つとして獣医療過誤の増加が挙げられますが、ペットの健康問題という意味では、ペットフードの問題は薬剤の問題と並んでよく相談が寄せられます。
例えば、ペットフードを食べたペットの体調不良、特定の成分を制限したペットフード(低アレルゲン食、低脂肪食まど)の副作用や病状悪化、ペットフードの使用量や使用方法の過誤など。
しかし、ペットフードの問題は、獣医療の世界だけではなく、広くペット産業、飼養者の問題でもあります。
そこで、今回は、獣医療問題からペット産業に繋ぐ架け橋としてペットフードの問題を取り上げたいと思います。
今回もそうですが、連載シリーズは全て渡邉弁護士に持ち込まれた実際の相談案件に基づいていますので、皆さまのお役に立つと思います。
(2)ペットフード(飼料)の安全性に関する法令の規制は、ペットフードの成分や添加物に関する規制とペットフードの表示に関する規制が典型です。人間の食品の場合と比較するとペットフードの場合は規制が簡略化されています。
順に説明していきます。
ペットフードには、保存料・酸化防止剤・安定剤・凝固剤・保湿剤・乳化剤・膨張剤・甘味料・調味料・香料・動物性油脂・着色料・発色剤などの添加物が含まれていますが、以下のような法的規制によってペットの健康・安全面の配慮がされています。
ア 目的
「動物の虐待の防止,動物の適正な取扱いその他動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し,生命尊重,友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに,動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命,身体及び財産に対する侵害を防止すること」を目的として制定されました。
イ 規制
動物を適正に飼養し,その健康及び安全を保持するよう努めることを動物の所有者又は占有者の責務としています(7条)。
「みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待」に対する罰則規定(44条)があります。
ウ 実務
動物愛護管理法は、ペットフードの安全確保全般についてまでは規定していません。
この法律は飼養者の飼い方にスポットライトを当てたものです。
飼養者がペットの飼養をしないで虐待する場合は決して稀なことではありません。多頭飼養が日常化しているペットショップ、ブリーダーなどの業務者や多頭飼育者の多頭飼育崩壊などの相談例があります。行政や裁判を通しての対応を検討することになります。
ア 目的
「飼料及び飼料添加物の製造等に関する規制,飼料の公定規格の設定及びこれによる検定等を行うことにより,飼料の安全性の確保及び品質の改善を図り,もって公共の安全の確保と畜産物等の生産の安定に寄与すること」を目的として制定されました。
イ 規制
飼料の安全確保に関する基準・規格の設定,有害物質を含む飼料等の製造・輸入・販売の禁止及び製造業者等に対する立入検査等を規定しています。
ウ 実務
本法の規制対象は,家畜等(家畜及び養殖水産動物)の飼料に限定されており, ペットフードは規制対象となっていません。当事務所の相談例の圧倒的多数は犬猫なので相談例もほとんどありません。
ア 農林水産大臣及び環境大臣が定めた成分規格及び製造方法に合わない犬及び猫用ペットフードの製造,輸入又は販売は禁止されます。
イ 規制
(ア)成分規格は、「愛玩動物用飼料の成分規格等に関する省令」によって使用してはいけない添加物等について詳細にリストアップされています。
(イ)製造の方法の基準は、次の通りです。
ペットフード協会は、ペットフードメーカーにより組織された業界団体です。 ペットフードの安全基準について、業界の自主基準として「安全なペットフードの製造に関する実施基準」 を策定し,国内外の製造業者に対してその普及を推進しています。
また、ペットフードの設計,原料購買,製造輸送・保管及びトレーサビリティの確保等に関する管理基準の策定しています。

「その食品の製造,加工又は調理の工程中において〇〇°で〇分間以上加熱するか,又はこれと同等以上の殺菌効果を有する方法で加熱殺菌しなければならない。」
「食品を製造し,加工し,又は調理する場合は,特定牛の脊柱を原材料として使用してはならない。」
ペットの場合にも、人間に準じた法的規制の仕組みを取り入れていますが、人間とペットの差異、監督官庁の所管の違い、業界団体の影響力などからペット規制は人間と比べて緩く、実効性には改善の余地があります。
販売される犬及び猫用ペットフードには下記の表示が義務付けられます。
人間だけではなくペットも対象とされますが、医薬品や医薬部外品等の広告規制に関する法律であり、ペットフード全般ではなく、生理的身体的効果があり薬機法の規制対象となる医薬品等に該当するペットフードが対象ということになります。
多くのペットフードが生理的身体的効果をうたっているので、医薬品等に該当するかは慎重に判断される必要があります。ここでは厚労省の医薬品の範囲に関する基準を紹介します。
ア 医薬品の範囲に関する基準
以上の4点を総合的に判断して「医薬品」と「食品」を区別し、いずれかに該当する場合は医薬品とみなされる。(参考:昭和46年6月1日厚生省薬務局長通知「無承認無許可医薬品の指導取締りについて」)
イ 広告規制
薬機法では、ペットフードが医薬品等に該当する場合には、医薬品等の認可を受けたものでなければ、その効能、効果又は性能に関する広告をしてはならないと定められています。また、以下の規制が規定されています。
① 虚偽・誇大広告等の禁止(薬機法第66条)
ペットフードの効能や効果、性能に関する虚偽・誇大な広告、獣医などが保証したと誤解されるおそれのある表現を用いた広告などは規制の対象となります。
② 特定疾病用医薬品等の広告の制限(薬機法第67条)
薬機法第67条では、がんや肉腫、白血病など特定疾病の治療薬に関する、一般人への広告を禁止しています。
特定疾病用の治療薬は効果が期待できる一方、強い副作用が発生するおそれもあるので、使用にあたって高度な専門知識が必要です。そのため、医師などの医薬関係者を対象にした広告に限って認められています。
③ 承認前医薬品等の広告の禁止(薬機法第68条)
薬機法第68条では、承認を受けていない医薬品等の名称、製造方法、効能、効果、性能に関する広告を禁止しています。
④ 具体的には、医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について(平成29年9月29日 薬生発0929第4号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)に定められているので、よく読んで検討することが必要です。
「不当景品類及び不当表示防止法」に基づき,ペットフード公正取引協議会が公正取引委員会の認定を受けた「ペットフードの表示に関する公正競争規約」を定め,適正な表示に努めています。
① ドッグフード又はキャットフードである旨の表示
「ドッグフード」,「キャットフード」,「愛犬用」,「猫用おやつ」等の言葉で表示しなければならない。
② ペットフードの目的の表示
給与の目的に応じて,「総合栄養食」,「間食」,「その他の目的食」のいずれかがわかるよう表示しなければならない。
③ 内容量
正味量をグラム,キログラムなどの単位で表示しなければならない。
④ 給与方法
ペットの年齢や体重に応じた給与量や回数等を表示しなければならない。
⑤賞味期限又は製造年月日
⑥ 成分
粗たんぱく質,粗脂肪,粗繊維,粗灰分,水分の重量比を%で表示しなければならない。
⑦ 原材料名
主要な原材料を使用量の多い順に記載しなければならない。
⑧ 原産国名
ペットフードの最終加工が行われた国名を表示しなければならない。
⑨ 事業者の氏名又は名称及び住所
損害賠償請求では因果関係の立証が最大の問題となります。
請求者は、ペットフードの製造販売に規制法違反の違法があり、ペットフードを食べたペットに何かしらの心身状態の悪化(損害)が生じても、その損害がそのペットフードを食べた結果として生じたメカニズム(因果関係)を獣医学的に証明しなければなりません。
また、ボツリヌス菌による多頭の被害については因果関係の相当性が問題となります。
これらの獣医学的証明には協力獣医との共同作業が必要となり、飼主は治療日記をつけ続けることが望まれます。
我が国ではペットフードの製造、販売など広い範囲で成分や表示の規制が制度化されています。
ペットフードを食べたペットの体調が悪化した場合には、そのペットの体調が悪化した原因を探索することになりますが、ペットの種類、年齢、性別などの特定情報、ペットの持病や治療歴、給餌の時間と体調悪化の時間的接近性、ペットフードの成分と体調悪化の関連性などを総合的に考慮して体調悪化がペットフードに起因するものか他の要因に起因するものか検討することになります。

最近目につくドッグサービス業の一つにパピーパーティー(幼稚園)があります。急成長を遂げているかどうかは別としてほとんど野放しの状態になっています。危険なパピーパーティーもありますが、誰も問題としていないので、急きょこのコラムで取り上げたいと思います。
パピーパーティーとは、犬の社会化を養うための手段方法の一つです。
社会化とは、幼少期の犬にいろいろな社会環境を経験させることにより、刺激となる環境に慣れさせ、不必要に感情的にならない状態をいいます。
いろいろな音や場所、生き物や雑多の人間などに慣れさせて社会性を身につけることが犬の発達にとって有効とされます。
生後まもない犬(3ヶ月〜6ヶ月位)にとっては、社会は見るもの聞くものがみな物珍しく、多種多様な刺激に満ちあふれています。
しかし、犬を飼った経験のある人ならば誰もが経験するように、犬同士の相性の問題と社会化の問題は少し違うようです。初めて会ったワンちゃん同士でも、こちらのワンちゃん自らが喜んで走り寄るワンちゃんもいるし、お相手のワンちゃんが喜んで走り寄って来るのにこちらのワンちゃんは嫌がって逃げたりします。
相性は、犬の犬種、原産国、性別、年齢などによっても異なるようです。相性の合わない犬同士を何日間一緒に生活させても、片方の犬にとっては地獄であると思います。
人間の幼稚園でも、仲の悪い子と仲の良い子ができ、いじめっ子といじめられっ子ができてしまうのと同じです。
そのため、人間の子供の社会化を図るために先生は専門的知識と経験に基づく指導とお手本を示しながら色々とご苦労されるのです。
犬の場合も同様です。犬種、年齢、性別、性格等による相性に配慮せずに雑多なワンちゃんを何時間も混入させ、人間が椅子に座って見張っているだけでは危険性と弊害の方が社会化よりも優ってしまいます。犬の傷害事故だけでなく、トラウマに苦しむ犬が現れます。
パピーパーティーの方法によって社会化を図るためには専門的知識と経験に裏付けられた適切なプログラムとトレーニングが必要となります。
犬の年齢、体格、犬種、性格などに配慮したグループ分けや遊びや遊具、しつけや正しいコミュニケーションを身につけるトレーニングなどが必要とされます。
パピーパーティーの共通の方法は、人間のトレーナーの監視下で犬同士が自由に遊び回るというものです。
問題は参加できる犬の対象ですが、現在多くのパピーパーティーは生後3ヶ月から6ヶ月のワンちゃんが小型犬でも大型犬でもが犬種を問わず合同で参加するものとなっていますが、中には年齢や犬種を問わないものもあります。また、動物病院が併設しているものもあります。
犬同士の傷害事故については法律の世界では犬の占有者(管理保管者)の注意義務が問題となるので、占有者は状況に応じた適切な方法で犬をコントロールしなければなりません。
他の犬とコンタクト(接触)する可能性のある場面でのノーリードはコントロールの放棄と捉えられても仕方がありません。
散歩では、リードによるコントロール、ドッグヤード内でも初めからノーリードとするのではなく、状況に応じてリードを使い分け、徐々に環境に慣らしていき、占有者も事故防止のため常に犬をコントロールできる距離にいて監視していなければなりません。
散歩やドッグヤードのケースではきめ細かい占有者の注意義務の内容やあり方が議論されてきました。
ところが、パピーパーティーでは、雑多な犬が最初からノーリードで放し飼いです。傷害事故の危険性は否定できません。散歩やドッグヤードのケースを参考にして、状況に応じた注意義務の内容やあり方を検討すべきであり、標準化すべきです。
人間のトレーナーの監視下で犬同士が自由に遊び回るというパピーパーティーの理念自体は理解できます。しかし、一定のルールがなければなりません。
例えば、犬の生命及び身体に対する危険を除去し、安全を確保するために、エリア内を参加犬の特性及び頭数に応じた適切な広さとすること、エリア及び関連施設の構造上及び人員上の安全措置を講じること、犬同士の不相当な接触による事故を防止するために、参加犬の種類、体格、年齢、性格に応じた分類分けをするとともにパーティーに参加できる参加犬に適切な制限を設けること、参加犬の種類、体格、年齢、性格に応じて行動エリアに参加犬の行動を制限する区分を設けること、相性の良い犬同士のグループ分けをすること、参加犬の頭数に応じた適切な人数の管理者(トレーナー)を参加犬をコントロールできる位置に配備すること、参加犬の種類や年齢や参加経験の段階に応じてリーシュ(統制綱)を利用するなどして、突発的な事故の発生に対して迅速に対応することができるようにすること、などの参加犬の生命身体に対する安全を確保するための適切な対応及び措置を講ずべき注意義務が考えられます。
いずれも、参加犬同士の自由な触れ合いを抑制するものではなく、適切なクラス分けと管理をしっかりと行う体制を作るということです。
電車に乗ってもバスに乗ってもみんな携帯に熱中し、公園で子供たちを遊ばせながら携帯に熱中する昨今、携帯が管理に影響を与えていないでしょうか。
犬の行動は予測できません。犬が突発的に危ない行動をした場合には直ちに制御しなければなりません。
パピーパーティーでは、管理者は雑多な犬を放し飼いにして何時間も注意深く見張っていなければなりません。携帯に熱中することはできません。
果たしてそんなことができるでしょうか。
管理者を管理する「管理者」は・・・いません。

渡邉アーク総合法律事務所
〒106-0032 東京都港区六本木7-3-13
トラスティ六本木ビル8階(東京ミッドタウン前)
0120-41-7565 または メールフォームで送る
予約は24時間受け付けています
原則として平日9:30~17:30
但し、24時間受付
予約で土日祝日営業時間外も法律相談対応