



「ペット」といわれて思いつくのは、犬や猫などでしょう。
また、小鳥、金魚、熱帯魚等もペットですが、これらの小動物は、犬・猫等とは一応区別して考えた方が良い場合があります(賃貸建物での飼育の問題)。法律上のトラブルが生じるのは主に犬や猫の場合なので、以下では、犬と猫を念頭において説明をします。
「ペット」をあえて漢字で表すと「愛玩動物(あいがんどうぶつ)」となりますが、現代社会では、ペットは「愛玩動物」では言い表すことのできない多種多様な役割や意味を持っています。また、ペットに対する人の見方や考え方も多種多様であり、人間との関係を考える場合にも、人間とは異質なものと解する人、人間の良きパートナー(伴侶)と解する人、人間と同質なものと解する人など様々な人がいます。このような社会的背景や人間の価値観の変遷によって、今やペットは人間にとってなくてはならない存在となりました。
ただ、注意しなければならないのは、ペットの良し悪しは、ペットに関わる人間によって決定づけられるということです。例えば、ペットを飼育する人によっては良きパートナーであっても、近隣住民にとっては、悪しき畜犬という例は枚挙に暇がありません。
ペットの騒音、異臭、等のペットの問題は人間関係の問題に他ならず、良好な人間関係を培うためにはお互いの配慮が必要なのです。

最近の当事務所に寄せられるペットを巡るトラブルは以前と比べると数も増え、トラブルの内容も多様性を帯びてきています。量的に増えていることは、ペットを人間と同等の価値のあるものと考えるペット愛好者が増えていること、ペット産業が急成長を遂げていること、ペットに対する認識や価値観が人によって大きく異なる状況となっていること等を背景としています。
問題は、ペットを巡るトラブルが質的に多様なものになってきていることです。今までは、ペットのトラブルというと、飼い犬に人や犬が咬まれて怪我を負ったという咬傷事故やペットにサービスを提供する動物病院や美容室(トリミング)内での事故が主要なトラブルでした。しかし、最近はこれだけに止まらないで、行政を巻き込んでの近隣被害(犬猫屋敷、犬猫のふん尿)や共同住宅内におけるペットの飼育に関するトラブル、ペットの所有権や利用権等の権利関係の有無や帰属に関する係争・・・等、枚挙の暇がありません。特に、これらの問題は、近隣社会や共同住宅の住民等多くの利害関係者VSペットの飼育者という対立構造を取るために、深刻な社会問題や訴訟に発展する可能性が極めて高くなっています。
また、ペットの交渉事故に限らず、マラソン競技実施中に観戦者が管理していた犬が、ランナーの走行中の車道に侵入したため、先頭を走っていたランナーが転倒するという事件が刑事事件に発展したことが耳目を賑わしたのは最近のことです。
このようなことから、明らかになることは、近時の傾向として、ペット飼育者の飼育方法や管理方法に対する社会的な期待や批判が強まり、飼育者に対する義務や責任が強まってきているということです。
当事務所では、このような新たな観点を加えて、より現状に即した多様な情報を皆様に順次提供していきます。
![]()
ペットをめぐるトラブルが、裁判所や自治体、弁護士に持ち込まれるケースが増加している。代表的なのは、過剰に繁殖させたペットが近隣の住環境を著しく悪化させる「多頭飼育崩壊」問題だが、それ以外にも「噛んだ・噛まれた」、集合住宅でのペット飼育など大小様々な問題が日々、発生している。
30年にわたってペット問題に取り組んできた渡邉正昭弁護士は「私が扱ってきたペットトラブルの内容は時代に応じて変わってきました。その一例として、5年前くらいから、近隣を巻き込んだトラブルや、相続問題とペットといった高齢化社会の影響が見えてきました」と語る。最新のペットトラブルの動向などについて詳しく聞いた。
一般社団法人「ペットフード協会」の発表(2017年12月)によれば、日本では今、犬と猫あわせて1844万6000匹が暮らしている(犬が892万匹、猫が952万6000匹)。
少子高齢化、単身世帯の増加、住環境の変化など様々な事情から、ペットと人間とが距離的にも心理的にも接近し、ペットが「家族の一員」となってきただけに、この30年で寄せられる相談は「時代に応じて、内容や性質が変わってきています」と渡邉弁護士は言う。
「当事務所では10年以上前までは、いわゆる犬の咬傷(こうしょう)事件ですね。噛んだ、噛まれたという比較的単純な案件が多かった。それが10〜5年前くらいから、さらに範囲が拡大し、契約上の権利関係をめぐる種々なトラブルが目に付くようになってきたんです」
典型的なのが、賃貸・分譲マンションでの「ペット不可なのに飼育している」「ペットの飼育許諾の条件に違反している」「ペットの飼育方法に問題があり、騒音や悪臭などで近隣に被害を与える」「突然の規約変更でペット不可になってしまった」など不動産賃貸契約や管理規約の解釈をめぐるトラブル。
また、「獣医師の医療ミス」「ペットショップで買ったペットに病気や先天性疾患があったことが後から判明した」「先天性疾患を隠されて買ってしまった」「トリマーが施術中にペットに火傷や怪我を負わせる、トリミングの仕方を誤る」などの売買契約や事務処理委任契約違反をめぐる相談も増えたという。
さらに、最近の5年間の特徴としては、相談内容が質的量的にさらに多種多様化し、解決方法についても法律の知識や経験だけでは対応が困難な事案が増えたことがあげられる。
「事務所の取扱い事件の最近5年間の特徴としては、法律の知識や経験では適切な対応ができない事案が増えてきました。たとえば、一人暮らしの高齢者が、犬の散歩を十分にさせることができなくなり、犬はストレスから無駄吠えを続けたため、近所の住民が苦情を述べたものの高齢者は言うことを聞いてくれない事案。ご近所の飼い猫が庭に入ってきて糞尿をすることを注意をしたら、かえって逆切れされて嫌がらせをされるようになったなどの事案です。
これらの事案では、初動のまずさから人間関係を悪化させ、トラブルを拡大させてしまっています。相手方を説得し、合意に至るための手法(例えば、交渉心理学やコミュニケーション技法の実践的知識や経験)が必要とされます。さらに、ニュースでも時折報じられる『多頭飼育崩壊』についても、同様な視点から対応することが必要です」
そして今、渡邉弁護士が注目しているのが「ペットの帰属をめぐるトラブルです。裁判例も増えてきていますね」という。
「たとえば、離婚する際や男女関係の解消の場合に、どちらがペットを引き取るかという問題、逃げ出したペットの所有者は拾得者か飼育者かという問題。そして最近、とみに増えてきたのが、相続や成年後見の場面で高齢の親が飼っていたペットを誰が引き取るかという問題です。
誰かが望んで手をあげてくれれば良いですが、皆が押し付け合うこともあるし、遺言書で取得者が決められていても,その方が取得することができなかったり、取得を拒んだりする場合があります。
飼育者が、将来ペットの面倒をみることができなくなることを想定して、第三者にペットの飼育を委託する契約を締結したり、いわゆる『ペット信託』を利用するという方法もあります。ただ、この場合でも、特定の誰かを指定する必要がありますし、ペットの飼育者の選定や飼育方法の問題は、財産の問題とは切り離せません」
そもそも、ペットのことを思えば、住環境は大きく変えないのが望ましい。しかし、「ペットの世話をしてもらう人に対して遺言書などで住宅も渡すことにすると、他に充分な遺産がないような場合には相続争いが起こりやすい」と指摘する。
時には、渡邉弁護士自らが里親探しに奔走することもあるそうだ。
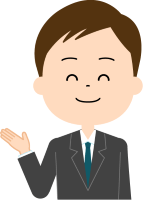
ペットの飼い主が知っておくべきことはあるのか。これまでの経験をもとに、渡邉弁護士は次の4つをあげる。
(1)ペットトラブルでは何より「初動」が肝心
(2)ペット関連の契約では「相手を素人だと思え」
(3)賃貸住宅では必ず「許諾条項」の確認を
(4)TPOにあわせて「リード」の長さを調整して
最近の傾向である、近隣問題に発展するケースでは、初期対応が何より肝心だ。たとえば、「鳴き声がうるさい」「糞が臭い」と近隣が思っても、愛情を持って育てている飼い主には、その認識がないこともあるそうだ。
「交渉においては、いきなり自分の立場や法律的要求を強く主張することは、相手方を過剰に刺激すると認識した方がいいですね。
意外に思われるかもしれませんが、相手に手土産を持って話に行く、自分の立場や要求をいうことを控えて、できる限り相手方の話をよく聴くようにするなど、相手方に与える刺激をできるだけ小さくしながら信頼関係を築き、その上でご自身の希望を聞いてもらえるような交渉をしていきましょう。初動を誤ると、相手も頑なになってしまい、トラブルが深刻化することになります」
2点目で言う「相手」とは、「ペット産業(ペットホテル、トリミング、ブリーダー、ショップ)」を指す。「こうした職種は国家試験があるわけでもなく、玉石混交だと思った方がいい。利用する時は、『すべてお任せ』が一番よくないですね。契約の段階で、契約書や関連書類のチェックをきちんとして、細かい点も確認しながら、細心の注意をはらって契約を進めてください」
3点目の賃貸住宅でのトラブルは、訴訟に結びつきやすいのだという。「『ペット不可だけれども、他の住民は飼っているから』と飼ってしまったり、ペット可物件でも騒音や臭いに配慮しなかったりすれば、トラブルに発展します。飼育の許諾条項があるからといって、万能ではないことも肝に命じてください」
時代を問わず、古くからあるトラブルが「噛んだ・噛まれた」のトラブルだ。これは(4)のリードを適切に使うことが有効だ。
「リードなしは問題外ですが、リードの長さや使い方次第では、飼い主の過失が問われる可能性があります。『うちの子は大丈夫』と過信せずに、リードを使うときの状況や目的、ワンちゃんの体格、性別、年齢、性格にあわせて対応して欲しい」
ところで、東京・六本木に事務所を構える渡邉弁護士。「ペット問題を扱い始めたのは、弁護士になってすぐですから、30年くらいになります」と言うが、きっかけは何だったのだろうか。
「私が動物好きだからです。子どものころから、猫ちゃんは常時20匹くらい、延べ100匹くらいは飼っており、ワンちゃんも3、4匹は飼っていましたね」
幼い頃から、動物と濃密に過ごした経験は、弁護士の仕事でも活用できているという。
「ワンちゃんは人間の言葉がわかりますが、猫ちゃんはワンちゃんほどはわからない。そこで、たくさんの猫ちゃんを飼っているときに、猫ちゃんを観察し、『修行』した結果、『怒っている』『悲しんでいる』『I miss you』。この3つの猫語をマスターしました。最近でも、初対面の猫ちゃんやワンちゃんとも気軽にコミュニケーションを交わすことができますし、向こうから寄ってくることもあります。弁護士としての仕事にも役立っています」
ちなみに現在のペットは、ワンちゃん一匹である。

1 ペットトラブルには様々なものがあります。
ペットの咬傷事故、里親をめぐるトラブル、ペットショップやペットホテルなどのペット産業界のトラブル、動物病院や獣医師の治療をめぐるトラブル(獣医療過誤)、離婚や遺産分割時のペット所有権の帰属のトラブル、ペットの葬儀や納骨をめぐるトラブル、騒音や臭気、多頭飼育といった飼い主と近隣間のトラブル、などあげることができないほど数多くのトラブルがあります。
2 しかし、全てが人間と人間の対立の問題であり、ペット同士の問題であっても人間と人間の対立の問題として検討しなければなりません。誤解している方がたくさんいます。
このことはペットトラブルに対処する場合には、常に意識しなければなりません。
3 人間同士の問題であれば、解決方法は、①交渉による合意、②判決による強制的解決、③経過観察による状況の変化、ということになります。
どの方法が良くてどの方法が悪いと言うことはありません。
事案と相手方の特性に応じて最もふさわしい方法を選べば良いのです。
ただし、ペット問題の解決方法として理想的なのは①の交渉による解決です。
しかし、現実と理想は大きく隔たっています。
現実は②の訴訟による解決が選択される場合が多い。
交渉を嫌う当事者、寝入りを待つ当事者、正義感情や信念、激しい感情的対立、ペットに対する認識の隔たりというキーワードが浮かんできます。
これらのキーワードを分析することは次回以降にし、今回は交渉による解決を実現するにはどうしたら良いかについて2つ指摘したい思います。
4 第1に、「できるかできないか(権利義務)」だけでは問題は解決しないということです。
権利義務と並んで「どういう風にすればできるのか、どういうことをしたらいけないのか」と言う交渉の仕方(交渉戦略・戦術)について検討しなければなりません。 権利義務については弁護士の専門分野であり、法律や裁判例でよってある程度答えを見つけ出すことが出来ます。しかし、交渉戦略・戦術については法律や裁判例の中に答えを見つけ出すことはできません。
法学部の試験問題ならば、出来るか出来ないか(権利義務があるかないか)という解答を出せばOKですが、実社会はそんな簡単ではありません。どのような手段・手続きで権利を実現するかという交渉が重要です。
権利があると主張しても相手方が応じない場合が普通ですし、権利があるかはっきりしない場合であっても、適切な交渉戦略や戦術を見つけ出せば説得と合意によってお互いが満足する解決をすることかできます。これらは心理学や法交渉学の分野の問題であり、法律では答えを見つけ出すことはできません。
5 第2に、交渉による解決を図るためには、当事者が事前に交渉のルールについて合意しておく必要があります。それは、いわば「交渉のための交渉」とも言えます。
それによって、お互いに信頼関係を作り出し、円滑な交渉を実現することができます。
しかし、このことに気がつく人はほとんどいないし、気がついても適切な交渉戦略や戦術を考え出すことができないために、お互いに不本意な訴訟や泣き寝入りをすることになってしまいます。
6 ペットトラブルの解決のためには、以上のことをきちんと理解しておかなければなりません。
訴訟はペットトラブル解決の方法として相応しい場合があります。しかし、訴訟を望まない依頼者も多くいます。
そのような場合は、重武装の訴訟よりも交渉による柔軟な解決の方が好ましいことは言うまでもありません。
ところが、交渉による解決が相応しいのに、最適な交渉による解決の機会を失い、安易に訴訟合戦へと突入してしまうケースが沢山あります。弁護士が心理学や法交渉学に不慣れなためです。
7 このような安易な傾向は改善されなければなりません。そうでないと依頼者は救われません。
当事務所では、「本当に訴訟が依頼者のためになるのだろうか?」いつもそのような問題意識を持って相談に応じています。
相談のときにも、権利義務の結論だけを求める相談者もいます。
しかし、それだけではペットトラブルは解決しないことを説明して、交渉戦略や戦術の検討します。
当事務所が法律相談で法交渉心理学の話をするのはそのような問題意識があるからなのです。
![]()
前回はペットトラブルの解決方法について全体像を述べましたが、その中でいくつかのキーワードを挙げました。今回はトラブルが発生した場合の初動(初期対応)について説明します。
なお、この文章もそうですが、私の書く文章は全て実際の経験と理論に裏打ちされたものです。
初動とは事件が起きた場合の相手方に対する最初の対応をいいます。
この対応が上手くできると早期の示談解決につながり、失敗すると解決困難な紛争の泥沼化に陥ります。
初動は極めて重要で、スキルと戦略が必要とされますが、多くの方は気づかないか、軽視しています。
当事者は、お互いに相手方を憎み、裁判をしようとし、相談を受けた法律専門家も裁判を起こしたら勝てると言う〜ペット訴訟の経験のない専門家が裁判の勝ち負けを語り、裁判を勧め、ペット訴訟の経験のない当事者が勝訴判決の自信を深め、裁判の決意を持
つ〜これがペット訴訟に至る多くの過程です。
問題は判決に至るプロセス(途中、誰が何をすべきか?)の認識が抜け落ちていることです。これは、誰も裁判をしたことがないのですから当たり前のことです。
ペット事件において、裁判を起こすことは実は難しいことではありません。裁判を維持する方がはるかに大変です。勝つためには必死の努力が必要ですが、自分だけではなく、相手方も必死の努力をしてきます。
勝つためには、時間、労力、資金、そして何よりも最後まで戦い抜く決意が必要です。
まさに裁判は「戦争」なのです。
だからこそ、初期対応の場面では、裁判に限定せずに、交渉も含めた複数の選択肢を準備すべきなのです。
その時点での最善の選択肢を、コスパのもっとも良い選択肢を選べば良いのです。
初めから裁判と決めてかかることは自分で自分を縛ることになります。他の最善な選択肢を失うことになります。
複数の選択肢の中から最善の選択肢を選ぶためには、法交渉心理学の知識と経験が不可欠です。
複数の選択肢の中から初期対応を検討した結果、裁判が最善の選択肢ということもあるし、交渉が最善の選択肢ということもあります。
また、交渉を選んだ場合でも、交渉の方法と戦略には複数の選択肢があるので、さらに交渉の中でもその時点での最善の選択肢を選ばなければなりません。
このような過程を経て、複数の選択肢の中から最善の選択肢が決まります。
このことから明らかなように、実はペットトラブルの解決方法は事案ごとに異なるオーダーメイドであり、ある決まった解決方法があるわけではないのです。ですから、他人の成功談もあまり当てにはなりません。
咬傷事故や獣医療過誤は裁判になりやすい。しかし、裁判によらないで示談解決したケースもあります。
その場合はお互いの代理人が交渉スキルとマインドがある場合です。皮肉にも、日本の弁護士よりは米国弁護士の方が示談解決がしやすいと思います。交渉に対する認識と姿勢には彼我の違いがあるからです。
選択肢を出来るだけたくさん持ち、その中からその時点での最善の選択肢を検討する心構えを持つことがペットトラブルの合理的解決のための唯一の「選択肢」なのです。
![]()
今回は、基本的な戦略とスキルについて簡単な事例をあげて説明します。
それぞれ異なった戦略とスキルを使ってます。どのような交渉戦略を使ったか想像できますか?
しかし、ある交渉戦略を使ったら問題が解決した。
加害者の犬は凶暴な大型犬、被害者の犬は小型犬、被害者は大怪我を負い、被害者の犬は死亡した。
加害者は責任を認めようとしないし、被害者をどう喝している。
しかし、ある交渉戦略を使ったら問題が解決した。
双方が代理人弁護士を立てて交渉している。
しかし、ある交渉戦略を使ったら問題が解決した。
もっとも、できるだけ広範囲で適用させようとすると行動指針として抽象的になり、実践性がなくなります。かといって、行動指針として実践性を持たせようとすると狭い範囲でしか通用しないものになります。
また、行動指針として、理論だけではなく、実践の場で実証され、実践に耐えられるものでなければなりません。
そこで、理論と実践のフィードバックの繰り返しで生み出された交渉戦略の体系が「フォーラムボックス」理論です。詳細は「法交渉心理学(連載)」で説明します。
以下、この理論に従って、上述の1から3の事例の交渉戦略について解説します。
近隣住民や役所の交渉が失敗した理由は何でしょうか? それは、相手方が問題行動者であると決めつけ、近隣住民が迷惑をするとの理由で、犬の無駄泣きを止めさせるように要求したからです。
「フォーラムボックス」理論ではこのような交渉戦略を「対立戦略」と呼んでいます。意図的な対立関係の醸成を目的とする戦略です。
近隣住民は思いに任せて交渉してしまったので場違いな対立戦略の結果が生じてしまったのです。
上手くいかない戦略は変更しなければなりません。
全く反対の立場を採ったらどうなるでしょうか?
相手方を問題行動者と決めつけない、理由は相手方が困っていることの相談にのり、相手方の手助けをすること、一緒に犬の無駄鳴きを解決する方法を考えようという立場で交渉したらどうでしょうか?
これが「信頼戦略」です。
カウンセリングや家事調停のラポール(信頼関係)を基盤とし、相手方の立場に立ち、相手方を説得する戦略です。
法律や論理は対立関係を醸成する危険があるので法律用語も含めて慎重に使用の有無を検討します。
交渉の結果、相手方は体が弱いために犬を散歩に連れて行けなかったことが犬の無駄鳴きの理由であり、相手方も改善意志があることが分かったので、みんなで話しあって合意し、近隣住民が輪番制で相手方の犬を散歩させることにしたら、犬の無駄鳴きが治りました。相手方は自治会費を支払ってくるというオマケまでつきました。
相手方(加害者)は責任を認めようとせずに被害者をどう喝しています(どう喝は対立戦略ではありません。)。
相手方の交渉スタイルは多くの場合過去の成功体験から学習したものですが、このような相手方に対して初動として信頼戦略をとると失敗する危険があります。
どう喝や威嚇が威力を発揮する場合はあります。しかし、自分で自分の首を絞めるリスクがあり、交渉のプロに対しては通用しません。
どう喝や威嚇をする相手方に対しては、相手方の思い込みを正すために、相手方にどう喝が効いていないと思わせる交渉スキルを実践することが先決です。
そして、こちらは対立戦略をとることを検討しなければなりません。
対立戦略は自己の立場に立ち、論理(法律など)的説得をするものです。
法律を使った説得は訴訟や権利義務の視点を全面に出すことになるので結果として相手方を威嚇する場合があります。
対立戦略を採用するかどうかは、相手方の性格や事件の性質、勝訴可能性、交渉資源などを総合的に検討しなければなりません。
事例2の場合は、早期に対立戦略をとり、訴訟上の和解によって相手方に請求金額全額を支払わせることができました。過去の成功体験から過度に攻撃的な交渉をする者は防御に弱い傾向にあることをまたしても実感しました。
ペット産業のトラブルの場合には請求者側(顧客)に弁護士が関与すると被請求者側にも弁護士が関与する場合が通常です。
弁護士だからといって交渉のプロとは限りませんが、幸にして双方が交渉のプロの場合には、紋切り型の権利義務があるかないかという書面交換だけではなく、紛争の拡大を予防し、依頼者のリスクとコストが最小限の交渉戦略を選択するはずです。
お互いに対立関係に入ることを回避し、信頼関係を築きながら、同時に論理(法律)の立場から、相手方の説得を試みる高度の戦略〜信頼関係に基づく双方の自制と均衡が崩れると対立関係を醸成し訴訟に至るという緊張関係に基づく戦略〜を採用できるはずです。これを緊張戦略と呼びます。
事例3の場合は、双方代理人が、緊張戦略を採用して、双方の認識に争いのある過去の事実関係や法律関係よりも、訴訟になった場合の将来の双方の利害得失に力点をおいた交渉をしたことによって、合意により解決しました。
信頼戦略=相手方の立場、対立戦略=自分の立場、緊張戦略=第三者(法律、権威)です。
また、信頼戦略→緊張戦略→対立戦略の順番で交渉をすることが原則です。
交渉戦略は理論と実践に基づく強力なツールであり、合理的な戦略的思考のない交渉はその場限りのものであり無謀としか言いようがありません。「初動」の場面から交渉戦略を検討しないと無謀だけではなく不毛の交渉となります。

渡邉アーク総合法律事務所
〒106-0032 東京都港区六本木7-3-13
トラスティ六本木ビル8階(東京ミッドタウン前)
0120-41-7565 または メールフォームで送る
予約は24時間受け付けています
原則として平日9:30~17:30
但し、24時間受付
予約で土日祝日営業時間外も法律相談対応